誇りが持てるマネジメント~組織開発(OD)の実践って、どうするの?-㊸~
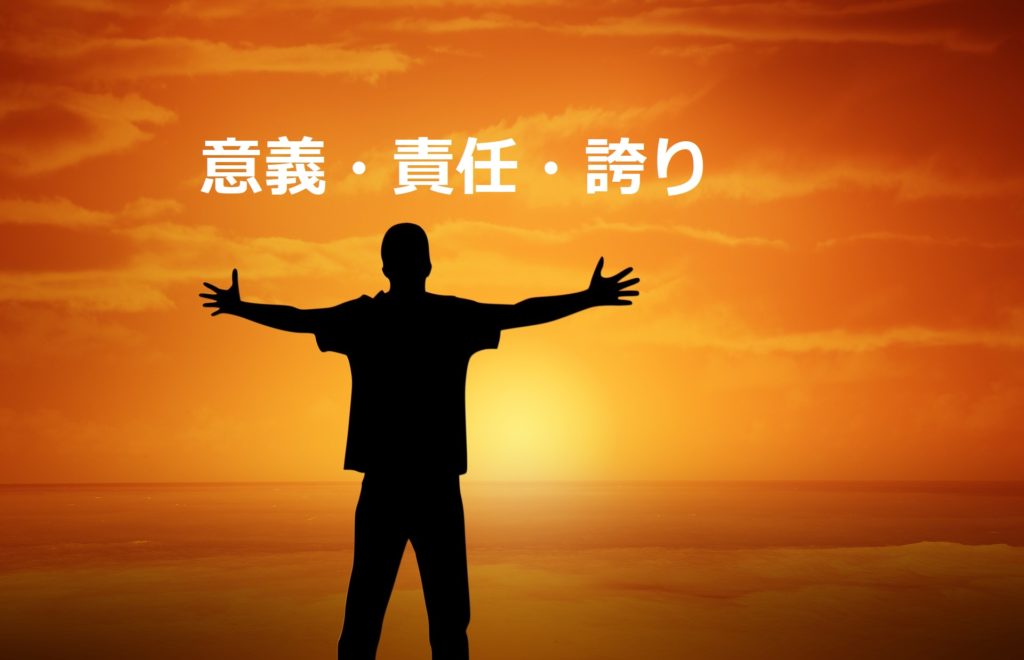
~黒部の太陽が泣いている~
「黒部の太陽」は木本正次による1964年の小説であり、これを原作とする1968年公開の日本映画です。映画では、三船敏郎と石原裕次郎のダブル主演で、特に迫力満点のトンネル工事場面は発表当時とても話題になりました。中学時代に映画を見てとても印象に残っています。また、10年程前に実際に黒部ダムを訪れ、その雄大さに感動し、殉職者の石碑を見て言葉にならない感情を抱いたことを思い出します。
このダムは、まさしく日本の高度成長期突入前夜における当時の関西電力経営者の意思と関係者の情熱と当時の最新鋭の技術がつくりあげた作品であるといえます。
なのに、どうしてなの。という怒りと情けなさ。かつて日本の未来を切り開いてきた組織の矜持はどこに行ったのか。いろいろ裏の話も出てきていますが、がっかりを通り越して言葉にならない乾いた無味乾燥な感情だけがぐるぐる回ります。
マネジメント研修や組織開発(OD)をやっていると、いろいろな要望やどうしたらいいのか質問、つまりhow to質問に出会います。
- ベテランと若手の融合はどうしたらできるか
- 若手のモチベーションアップをどうしたらよいか
- 多様性を活かすといってもそのマネジメントはどうするの
などです。
で、どうするかですが「こうすればうまくいくといった都合の良い方法、つまり正解はない」が答えです。つまり、正解はある特定の状況の中での正解であって「あなたの組織もそうすればうまくいく」という保証はどこにもないのです。例えばここ数年、ビジネス本でも話題になったマインドフルネスやアンコンシャス・バイアス。
それもGoogleが導入したということで話題になりイベント講座みたいなものも沢山開かれています。それで「よし、我社も」と挑戦するのは良いのですが、うまくいくやり方を教えてと、how toを求める方々が結構多いのですよ。
組織変革(OC)でも、ジョン・コッターの8つのステップは有名ですね。それは「①.危機意識を高める⇒②.変革推進チームをつくる⇒③.ビジョンと戦略を生み出す⇒④.ビジョンを周知する⇒⑤.従業員の自覚を促す⇒⑥.短期的成果を実現する⇒⑦.成果をテコにさらなる変革を進める⇒⑧.新しい方法を定着させる」というものですが、ある企業でトップがあんまり危機を煽り立てたので「こんな会社にいられない」と、優秀な連中が辞めていったという話や、成果をテコに「もっとやるぞ」と社長が宣言すると従業員から「疲れているんですけど」と、ギブアップや不満の声が上がったりと、要するにモノゴト予定調和のようにうまくいかないのですよ。
コッターだって限られた経験の中でいっているわけで、実行する時は当該組織の固有の状況を考慮して変革のデザインをしていかなくてはならないのです。
誤解がないように言いますが、ある特定の問題を解決しようとすればそれは検証されたエビデンスに基づく裏付けが必要です。前回のODメディアで紹介したレジリエンスを高めるプログラムであるPRP(ペン・レジリエンシー・プログラム)は効果が立証されたプログラムです。
しかし、ロナルド・A・ハイフェッツがいう「適応を要する課題」には、技術的問題解決のように「これこれこうすれば良くなります」という正解はないのです。なぜなら、組織は「事業が異なるし、構成員が異なるし、関係性が異なるし、文化が異なるし、状況が異なる」からです。
考えても見てください。Googleってどんな組織ですか。世界を変える野望を持った創業者が「1クリックで世界の情報へアクセス可能にする」をビジョンにして、それに共鳴した超優秀な若者が世界中から引き寄せられ、企業内起業家的な動きを推奨し、高額な給与を支払っている会社です。そんな会社が導入したマインドフルネスやアンコンシャス・バイアスなのですよ。
むしろ、Googleだからそれが求められたのです。そういう環境にない企業は、ではどこから始めるか、「マインドフルネスをやるぞ」じゃ福利厚生で終わりですね。現にGoogleだって最初は福利厚生の一環で始めていますから。
~ポジティブって楽ではない~
ポジティブ心理学が日本でも関心を持たれています。日本企業はエンゲージメントが低いだとか、モチベーションが低いだとか、いろいろネガティブなことを言われ、いやそうではなくもっとポジティブに生きようとか、今いる場所で花を咲かせようとか主張する向きもありますが、ポジティブってお花畑で仕事をすることじゃないんですよ。
ポジティブって快楽とは違います。本来は厳しいものです。「幸せ~~~て、ポン酢しょうゆがある家さ(1986年CMキッコーマンポン酢しょうゆ)」じゃないです。
もちろん、幸せの中には情緒的な快楽はありますが、それは一時的なモノです。持続的な幸福感を得るには「自分がやっていることに意義を感じること」が必要です。仏教用語でいうところの「自利利他」が必要なのですよ。自利利他には当然「自分がやっていることに責任を持つ」という事を含みます。これがあっての良好な人間関係であり、ポジティブな感情であり、達成感な訳です。
そして、「自分がやっていることに意義を感じること」「自利利他」というのは私たちのエゴではなく、関係する人たちとの関係性の中で成り立つものです。それはなぜかといえば、私にとって意義あることは、相手にとっても意義あることではないからです。だからこそ異なる欲求やニーズあるいは価値観を前提にした「違いを乗り越える対話(ナラティブ:世界を見る見方を話し合う)」が必要なのです。
どこぞの助役や関電の幹部のナラティブは、世間のナラティブとはズレているのですよ。そんなことはみんな分かっている筈なのに。ズレを認めるのは実は厳しい世界です。これまでの関係性が壊れるかもしれませんし、自分が築いてきた世界観を捨てなくてはなりません。でも、組織開発(OD)ってそういう事なんですよ。
組織開発(OD)というアプローチをやってみたいと思うきっかけはいろいろあると思いますが、最初にやるべきことは「わが社は、我社で働く人たちが本当に誇りをもって働ける組織になっているのか」から検証すべきです。ここが不十分であると「またぞろどこかの借り物の手法でヒラメ改革(上に気に入られる改革のこと)をやり始めた」と従業員に思われるだけです。
この記事の書き手はJoyBizコンサルティング(株)波多江嘉之です。

![[組織開発]教科書から学ぶ①~何がODなのか 組織開発(OD)の実践って、どうするの?-245~ no-image-square](https://www.joy-biz.com/wp-content/uploads/2019/02/no-image-square.png)
![[組織開発]教科書から学ぶ②~ODのルーツ 組織開発(OD)の実践って、どうするの?-255~ [組織開発]教科書から学ぶ②~ODのルーツ 組織開発(OD)の実践って、どうするの?-255~](https://www.joy-biz.com/wp-content/uploads/2023/12/画像1-270x270.png)